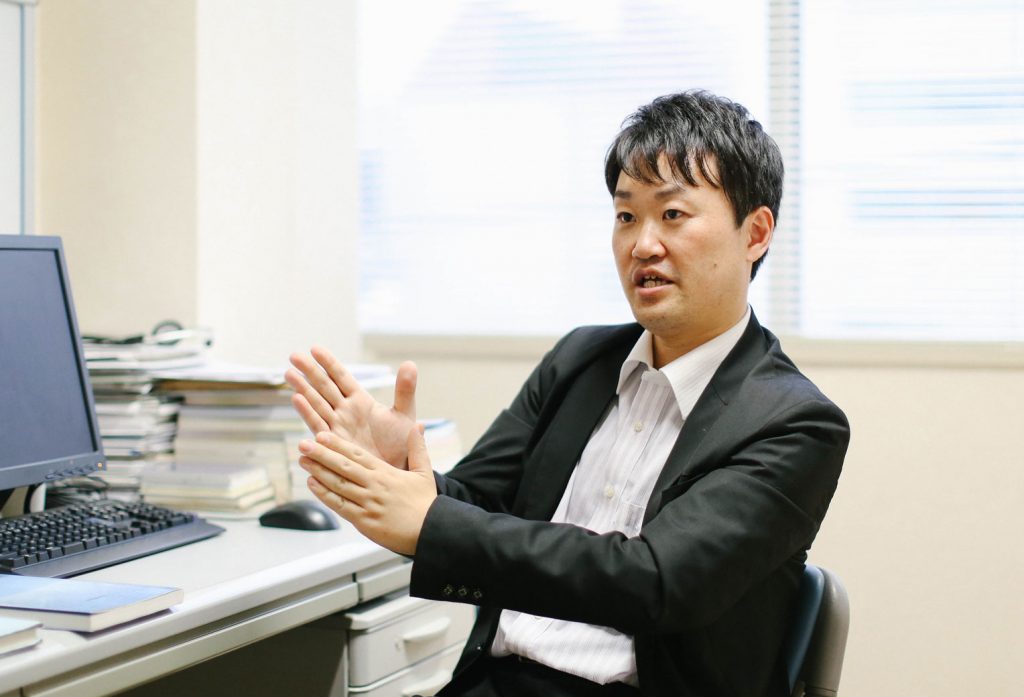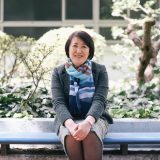緩和医療医であり、早期緩和ケア大津秀一クリニックの院長を務める大津秀一さん。『死ぬまでに決断しておきたいこと20』をはじめ、「人生の終末を迎えるための準備の大切さ」について、講演や著作で積極的に発信されています。「人に臨む“臨人医”でありたい」と願う、大津先生の本に込めた想い「ほんとのはなし」お届けします。
こんな話をしています……
・床に臨む臨床医ではなく、人に臨む“臨人医”
・患者さん達の言葉が今の自分を作ってくれた
・死を考えるということは生を考えること
大津秀一(おおつ・しゅういち)氏プロフィール
早期緩和ケア大津秀一クリニック院長
茨城県出身。岐阜大学医学部卒業。 内科専門研修後、日本最年少のホスピス医(当時)の一人として京都市左京区の日本バプテスト病院ホスピスに勤務したのち、平成20年より東京都世田谷区の入院設備のある往診クリニック(在宅療養支援診療所)に勤務し、入院・在宅(往診)双方でがん患者・非がん患者を問わない終末期医療・緩和医療を実践。2010年6月から東邦大学医療センター大森病院緩和ケアセンターに所属し、緩和ケアチームを運営。18年8月、緩和ケア専門として都内に「早期緩和ケア大津秀一クリニック」を開院、院長を務める。 著書に『死ぬときに後悔すること25』(致知出版社)、『死ぬまでに決断しておきたいこと20』(KADOKAWA/メディアファクトリー)など。
人に臨む“緩和ケア”
――“緩和ケア”について伺います。
大津秀一氏: 私が所属する「東邦大学医療センター大森病院」における緩和ケアでは、常時20人以上の入院患者さんと、外来に通院されている患者さんを、主治医の先生と一緒に診察させていただいています。症状や病状も様々で、関わり方は非常に多様です。症状を和らげる医療を提供することもあれば、終末期を見据えた決断の支援で関わることもあります。
私たちは精神科医や臨床心理士、薬剤師やリハビリの専門家と連携して、患者さんを支える方法を色々と提案しています。私は床に臨む臨床医ではなく、人に臨む“臨人医”だと思っています。患者さんと面と向かって関わり合い、最期まで生活の質を向上するためにできることを探すのが緩和医療医であり、それを実現するのが“緩和ケア”だと考えています。
私は小さいころ、体が弱く非常につらい思いをしました。病床にあった地獄全図のような本を読み、「死後の世界」を考えるような子どもで、体や病気そして死について、幼い頃からたびたび触れる機会があったのです。高校生のころは文系で、世界史など人類の営みと闘い、栄枯盛衰の歴史に惹きつけられましたが、特に倫理の教科書の副読本に書かれた、哲学者の人生や苦闘の物語を「生い立ちが思想に影響することはあるのか」などと考えながら興味深く読んでいた記憶があります。
けれども高校3年生の進路選択で、幼少期の体験が蘇ってきて「体が弱くて病気がちだったからこそわかることがあるのではないか。そういう医者も必要なのではないだろうか」と思うに至り、医学の道に進むことを決めたのです。
患者さん達の言葉が今の自分を作ってくれた

大津秀一氏: 今の医学生は早期に医療現場の実習などを体験する機会も増えているようですが、私たちの頃ですと、最初の1年間はもっぱら医学以外の学問修得に充てられ、内科学などの臨床医学の勉強も4年生になってからでした。5年生から病院実習が始まって、実際に患者さん相手の見よう見まねの実習が始まります。
山奥からはるばる来ている肝臓ガンの患者さんの話から、無医村の問題や交通の便と医療の問題が直結する現状を知ることができました。また、患者さんの悩みは病気そのものだけではなく、生活や経済的問題、仕事や周囲の人との関係など多岐にわたるということにも気がつきました支えるということは、薬や医療ばかりではない。
ひとりひとりのお話を伺って、耳を傾ける重要性を感じたのは、この頃です。振り返ってみると、この頃に出会った患者さん達の言葉が今の自分を作ってくれたんだと思います。話をしてくれた患者さんの、喜ぶ様子がとても印象的で、今でも忘れることができません。
患者さんの悩みに対して試行錯誤する中で、また多くのことを学ばされました。最初に就職した病院では消化器内科にいましたが、そこではがんの患者さんが、患者さんの症状を和らげるために治療をしていたのですが、なかなか患者さんの苦痛をとりさることができず、また治療のかいなく終末期に移行していく様を見届けなければならないことに悩んでいました。
そんな時に、淀川キリスト教病院(現京都大学)の恒藤暁先生の『最新緩和医療学』(最新医学社)という本に出会いました。内科学の本というと普通、食道がんや胃潰瘍など、病気ごとに、診断、治療の仕方などが書かれているのですが、この本は、痛みやだるさという「症状」ごとにその原因、治療法がこと細かに記されているものでした。「症状を和らげる専門の治療がちゃんとある」ことに衝撃を受け、当時携わっていた治療に役立てようと何べんも読み返していました。
「痛い、苦しい」と言う患者さんに、それまで型どおりの治療をやっても全然よくならない。けれども、この本の通りにやると、例えば胸の水がパンパンにたまって、苦しくて動けない患者さんも、ステロイド薬で、胸の水が減って動けるようになるなど、がんの終末期の様々な苦痛が、適切に薬を使うことで緩和されたのです。この喜びと驚きからますます緩和医療に惹かれていき、現在の道につながっていきました。

「死を考えるということは生を考えること」
大津秀一氏: 多くの患者さんと臨む中で、「悔いのない時間を過ごすこと」がとても大切だと今は感じています。すべての患者さんが「やるべきことはやった」と、後顧の憂いなく逝けるというわけではありません。がんも最近は症状緩和の技術が進んで、かなり遅くまで良い状態でいられるものの、やりたいことや言いたいことを言えずに最期の時間を過ごすことになってしまう例は少なくないのです。本人も心残りですし、家族も後々まで悲しむということになります。もっと話し合ってほしいという想いは、近年ますます強くなってきています。
『死ぬときに後悔すること25』(致知出版)には、そうした想いを込めて書きました。みなさんやはり後悔はしたくないと思われていますが、そうならないためには、日々の決断が大事です。「生き死に」の問題は、できるだけ考えたくないという風潮がありますが、やはり避けては通れない問題で、できれば健康なうちから少しは考えておくのが良いし、今もし残り時間が相当限られているとしたら何を自分は本当に望むのだろうかという問いを行うことは、今ある「生」を豊かに過ごすことにつながると私は考えています。「死を考えるということは生を考えること」。そして、それは決して一人で考えるだけではありません。なく、ご家族とも話し合い、お互いがどういう価値観を持っていて、何を希望しているのか、それをよく理解しておくことが大切です。
私が最初に本を出した2006年当時、緩和医療に対する認識は、今とは比較にならないものでした。浮かない顔をされた患者さんにわけを聞くと「みんなに勧められてホスピスに来たけど、何をされるのか不安です」とか「ここは終末期のうば捨て山のようなところだと聞いた」という返事が返ってきたこともあります。そうじゃないということを説明する中で、もっと広く社会に、緩和医療について発信しなければいけないと思うようになりました。最初の本『死学 安らかな終末を、緩和医療のすすめ』(小学館)はそうしてできた本でした。
――そうした発信から緩和医療に対する認識は、どんどん変わってきました。
大津秀一氏: これからは、“価値観に沿う医療”がますます重要になってきます。老年期医療や慢性期医療、がん医療……可能な限り長生きするために治療をできるだけ受けたいという患者さんもいれば、短くても苦痛だけは取ってもらって好きに生きたいという患者さんもいます。患者さんとの対話を通して、患者さんの価値観を理解し、それに沿った医療やケアを実践する、医療者と患者さんがコミュニケーションを深めながら、協働作業として緩和ケアは存在します。
そのための一助となるべく、現場のことをわかりやすく本にすることも私のライフワークです。そして私自身は、一臨人医として患者さんと接して、痛い苦しい、あるいは心の苦しみや様々な悩みに困っている方、そして重い病気で死と直面している方々を支えていきたいと思っています。