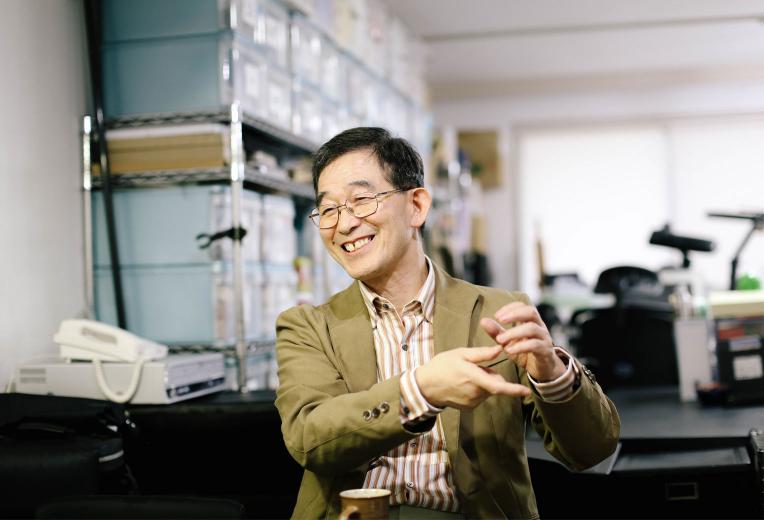こんな話をしています……
・デザインの三原則は「相手を笑顔に、喜ばせる」「感動させる」「人を幸せにする」
・色には塗った人の気持ちが表れている
・悩み続けるより解決の仕方を学び、結果がどうであれやってみる
1944年東京都生まれ。金沢美術工芸大学産業美術学科卒業。 グラフィックデザイナー、アートディレクターとして活躍。また、ベーシックデザイン、デザイン理論、表現技法、色彩などの分野で新しい理論を打ち立て、研究と実践を行う。特にデジタル色彩では日本の先端にいる。1990年に株式会社ハルメージを設立し、グラフィックを中心としたデザイン活動を展開。 著書に『100の悩みに100のデザイン』(光文社)、『色と配色がわかる本』(日本実業出版社)、『デジタル色彩マスター』(評言社)、『視覚デザイン』(ワークスコーポレーション)、『レイアウトデザイン―レイアウト基本マニュアル』(グラフィック社)など多数。
“先端色彩”を伝える
――デザインを軸に、様々な活動をされています。
南雲治嘉氏: ぼくが代表を務めるハルメージでは、専門領域であるグラフィック系のものを始め、ウェブや動画、サイン計画やブランディングなど、幅広いデザイン活動をしています。またぼくの領域である“先端色彩”についても、様々な場所でその想いを伝えています。
デジタルハリウッド大学では、色彩関連と、アイデアの発想論の二つを中心に担当しています。ここでは、常に先端のものを求められますので、それを授業で生かしたり、多くの方にセミナーなどで発信しています。
――日本にとどまらず、中国でもご活躍されています。
南雲治嘉氏: 今の中国では「日本のデザインや考え方などを丸ごと学びたい」という意欲があります。中国メディア大学や上海音楽学院の教授の就任要請もそのひとつです。いわゆる「爆買い」と呼ばれる大量購入の背景にも、日本のデザインに対する信頼があるからなのです。これからはデザインで経済を発展させるため、日本のやり方を学べということで、色彩関連、デザインを教えています。学生は、純粋で素直で、とてもしっかり勉強をしてくれるので、感心しています。
「色」というのは、人間に大きな影響をもたらします。それは単に美しさを感じさせるだけでなく、視覚的なことや色を見ることは、脳への刺激であり、ホルモンの分泌に関わっており、体や心の反応につながっているのです。 色は電磁波ですが、例えば赤が網膜にあたると、網膜にある視細胞がRGBのデジタル信号に変換し、視床下部に伝えます。赤は780ナノメーターという電磁波であるため、それが刺激となりアドレナリンの分泌を促します。一方で視交叉を経て脳の後方にある視覚野(モニター)に赤を影像として映し、人間は赤を知覚(見る)します。人間の五感の刺激は視床下部に集中します。
“色”は人を幸せにする
南雲治嘉氏: 色に対する想いは、グラフィックデザイナーである叔父の影響を強く受けました。叔父は、ぼくが小さい頃から新聞に載ったり、国際的な賞を獲ったりしていて、子ども心に「かっこいいな、すごいな」と憧れていました。小学校1年生の時には既に、「デザイナーになりたい」と作文に書いていました。
日本の色彩教育の基礎を作った人でしたので、ぼくにも、色に関する課題を出してきました。5㎝四方の布や紙を毎週100枚ほどくれて、「ポスターカラーで、そのままそっくり色を塗れ」と。「まず色を知らないと配色ができないから、色出しができるようにしなさい」というわけです。色の組み合わせや、色の表現の仕方など、知らず知らずのうちに叩き込まれていきました。おそらく7000枚近くの種類を作らされました。また「色には塗った人の気持ちが表れている」との“色からのメッセージ”も教わりましたね。それが文字通り“色々と”役に立ちました(笑)。 ぼくには、3歳年下の妹がいるのですが、小学2年の頃妹のために絵本を描いたことがありました。それを見たお袋は、「この子は絵の世界に」という気持ちになったそうで、毎月1回は必ず美術館に連れて行き、そこで絵の解説をしてくれていました。お袋の指導もあって、コンクールでは、連続して総理大臣賞などを獲っていきました。 ところが親父は、自分が日本画家だったにも関わらず、僕がそういう世界に行くことに反対していました。いや、日本画家だからこそ、同様に飯が喰えないデザインに不安を持っていたのかもしれません。安定した理工系に進めということで、高校は理系のクラスに籍を置きました。そして、すすめられるままある国立大学を受けたのですが、落ちました。でもそれがかえって良かったかなと思います(笑)。 予備校へしばらく通ったのですが、絵を描くことを諦めきれず、お袋に相談しました。デザイナーである叔父に説得を頼んでくれたようで、叔父は親父に、「子どもにはやりたいことをやらせろ。それで失敗しても、その子が選んだ道だからいいじゃないか。もし理系に進んで失敗したら、お前の責任だぞ。今まで見てきたけど、あいつはデザインの世界に向いている。だからやらせてやれ」と。それで、ついに親父が折れてくれたのです。
貧乏学生と、お嬢様「マチコ」の出会い
南雲治嘉氏: そうして金沢美術大学に進みました。デザインの勉強ができることがうれしかったです。それとは別に金沢美大では「劇団に入っていないような人間は、人前で話すことが出来ない」という考え方が蔓延しており、ほとんどの人が劇団に入っていました。ぼくも先輩に誘われるがまま、三つの劇団に所属していましたが、卒業後も病み付きになるほどでした。
今でもデジハリで劇団を作り、学生たち公演をしています。時々映画のオファーもあるのですが、最近はおじいちゃん役や、死んだ人を頼まれることが多く、ちょっと不満でもあります(笑)。けれども、常日頃劇団の団長として、学生には「オファーがくれば、断らずにやりなさい」と言っている手前、文句は言えません。映画や演劇など集団で作っていく表現もあれば、ひとりで絵を描くなど、色々な表現の形態を知っているのは、大切なことだと思います。 そんな充実した大学生活も4年目に入った頃、課題「子供」の絵を描くために、河川敷に行ったのですが、そこで小さな子どもを連れた女性に出会いました。のちに妻となるマチコです。彼女の優しく、純粋な雰囲気に惹かれて、次の課題「若い女性」のモデルになってもらうべく声をかけました。その時は「わかりません」という返事しかもらえませんでしたが、後日、待ち合わせの場所には来てくれました。最初は河原に行ったのですが、もっと見晴らしの良い公園で描きたいなと思い「上に行きましょう」と土手の下にいたマチコの手を引っ張って連れていきました。それが6月1日。それからずっと描き続けていました。9月23日の秋分の日に、いつものように公園で絵を描いていたときに、とんでもないことを言われます。「私はもう、あなたとしか結婚できない体になってしまった」と。
――先生、何をされたんですか??
南雲治嘉氏: こちらは何も身に覚えがありません(笑)。それを言うと「6月1日のことを忘れたんですか?あなた、私の手を握ったじゃないですか」と言って泣かれました。
旧家のお嬢様だったマチコにとっては、異性と手をつなぐなんて、よほどのことだったのです。けれどもぼくの方は、貧乏学生です。マチコのお父さんも当初は賛成という雰囲気ではありませんでした。ところが卒業したその年、金沢の海水浴場で、おぼれたマチコを助け、それを知ったお父さんから「命を張って助けるような男に、おれは何も言えない。結婚しろ」と無事、承諾してもらえました。 結婚して1ヶ月ほど経ったある日、実家に帰っていたマチコから絵を描いた公園の出っ張りを買ったよ、との電話がありました。前に「この公園は、自分で探し回って見つけた最高の場所で、本当は誰にも教えたくない場所なんだ」と話したことの返事がこれだったのです。ぼくの思いを実現するために勝手に、買ったとのこと。「もうあそこはあなたのものよ~」と(笑)。そこは今でも自分の土地なのですが、その時に「この人はちょっと不思議な人だな」と思いました。「お金どうするの?」と聞くと、「あなたが稼げばいいじゃな~い」と言って銀行から借りさせられました。
――奥様の後押しが、原動力になっているのですね。
南雲治嘉氏: ぼくをここまで支え、夢を後押ししてくれたのはマチコです。「夢というのは実現するためにあるの。気安く夢を語るような人になってほしくない。あなたが言った夢は全部実現するから」と言います。自分の能力を超えていることをやらせるというか、ぼくがやったことのほとんどは、マチコがぼくの夢を実現させるために仕向けたことなのです。
マチコにはお茶目な一面もあります。ある日、ぼくの芝居に誘ってみたのですが、風邪を理由に「残念だけど家にいて療養します」といいながら、実は隠れて観に来てくれたこともあります。隠れて見に来てくれた理由を尋ねると「私が行くと知ったら、あなたは絶対に舞い上がってしまうでしょ?」と。そういう茶目っ気のある人でもあります。結婚して45年間。今もずっとお弁当を作り続けてくれていますし、朝の見送りもしてくれています。素晴らしい女性だと思います。ぼくは今まで、一人で頑張ってきたのではなく、常に二人三脚でやってきました。だからぼくは、サインはマチコへの感謝を込めて二人の絵を書きます。二人で一つの人生を送っているのです。
――本ができあがった時なども、マチコさんに見せるのですか。
南雲治嘉氏: 家で書いている姿を見ていて、応援してくれています。マチコが笑顔で「これ、いいね」と言ってくれた本は必ずヒットしますし、「これはつまらない」と言ったのは大抵ダメです(笑)。『100の悩みに100のデザイン』を見せた時は、「こういうのが伝わるのよ。面白いあなたの考えが全部入っているじゃない」と言ってくれましたが、実際にその後、多くの方に読んでもらっています。
デザインで豊かな人生を
――どういった思いで書かれた本なのでしょうか。
南雲治嘉氏: ぼくの会社の客様は色々な悩みを持ってきます。全く想定していない人事の問題まで依頼されたこともあるのですが、デザインという切り口で企画提案し成功したのです。問題のテーマを考え、背景を探り、解決方法を考え、そこに至る道を計画し、実行する。こうしたデザインの手法は、領域を超えて通用するのだと気づき、それを伝えるために書いた本です。
「解決できない問題はないんだよ」ということを伝えたいのです。悩み続けるより、解決の仕方を学び、結果がどうであれ、やってみる。そうすることで、自分の気持ちが軽くなります。デザイン手法を用いれば、苦しみも軽くなるのではないでしょうか。それは、私が学生に伝えている「人の幸せ」につながると思っています。 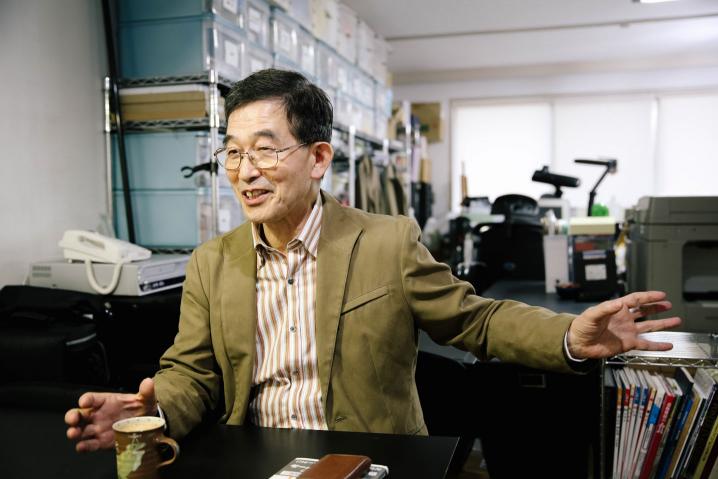
――叔父さまの想いを継承して……。
南雲治嘉氏: 叔父は色彩の先駆者であり、“色”は人を幸せにするという、叔父の想いを引き継いで、これまでやってきました。今は、後進を育てなければいけないという段階です。日本、中国で教えている学生たちが受け継いでくれて、発展させてくれるだろうと思っています。叔父や叔父の親友でもあった、世界的な色彩学者ヨハネス・イッテン先生、それと叔父の弟子でもありぼくの師匠でもあった太田昭雄先生から受け継いだものを、今度はぼくが若き人たちに伝えていきたいと考えています。
この間マチコから、「普通、私たちの年齢になったら、定年、老後っていう段階にきていると思うのだけど、私たちはいつになったら二人で旅行に行けるの?」と言われて、「やばい!痛いところをついてきたな」と思いました(笑)。