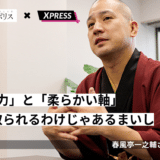![]() by 沖中幸太郎
by 沖中幸太郎
こんな話をしています……
- 単純で強い憧れこそが、すべての出発点だった
- 「自分が心底感動させられた」世界を見てしまった以上、そのまま不本意なことをやり続けるわけにはいかなかった
- すべてを失って体当たりで進んだ結果、どん底と思われた状況は、結果的にまた、今のカンジヤマ・マイムに欠かせないものとなった
- 自分の感動した体験を信じ続けること
藤倉健雄(ふじくら・たけお)氏プロフィール
カンジヤマ・マイム主宰 Ph.D (教育演劇学博士)。早稲田大学国際教養学部(SILS)、および上智大学国際教養学部(FLA)講師。ニューヨーク州立大学演劇学部修士課程を経て、ウィスコンシン大学演劇学部博士課程修了。アメリカマイムの巨匠、トニー・モンタナロ氏に長年師事し、米国内の様々な大学にてマイムや教育演劇のクラスを指導する。マイム歴40年。マイム、教育演劇に関する著書、訳書、および論文多数。中でも2008年日本の教育演劇に関する博士論文が、アメリカ 教育演劇協会より最優秀論文賞を受賞した。NHKテレビ「おかあさんといっしょ」の身体表現コーナー「パント!」の振付、監修担当、また、NHK国際放送「日本語クイックレッスン」のマイムコーナー「Grab it!」の振付を担当し、自ら出演している。公式ウェブサイト(www.kanjiyama.com)
「感じる心が山もり!」の想いを込めて名付けられたパントマイム集団「カンジヤマ・マイム」。主宰するのはマイム歴40年の藤倉健雄(カンジヤマ・マイムA)さん。「無口で、白塗りの大道芸」という従来の常識を破り、観客を積極的に引き込む“おしゃべりな”パントマイム芸は、多くの人々の心を掴んできました。故永六輔氏をはじめ、数々の著名人からも愛されてきた独自のパントマイム芸。その世界観はどのようにして生まれ、磨かれていったのか。「すべては感動からはじまった」と語る藤倉さんの、原点、挫折と挑戦の軌跡を辿りながら、そこに込められた「感動」を伝える想いを伺ってきました。
「おしゃべりな」カンジヤマ・マイムの秘密
――心を掴む、「おしゃべりなパントマイム」が好評です。
藤倉健雄氏: カンジヤマ・マイムは、現在ぼくAのほか、B、Cと3人のメンバーで、全国各地の学校、文化会館、病院、その他養護施設などさまざまな場所に呼ばれてパントマイム公演を行っています。少ない月で7〜8本、多い月でほぼ毎日、どこかに出かけています。
長らく、パントマイムとは、「無口、白塗り、大道芸」というイメージが定着し、どこか普段の自分たちとは「違う」世界と思われがちでした(もちろんそうした世界観も魅力のひとつなのですが)。しかし、パントマイム芸能の幅広さ、面白さをもっと多くの人に知ってもらいたい、身近に感じてもらいたいと、ぼくたちは沈黙を破り、舞台の上でしゃべりはじめました。
パントマイムに必要なのは、「自分の内なる独自性」を発見し、表現することです。ぼくたちはつい、自分に足りないもの、欠けているものに目がいきがちですが、すでに身体という素晴らしいものを持っています。足りないものは何もない。ただ自分が持っているはずの宝、身体と想像力による独自の可能性を掘り出しさえすればいいんです。マイムという「鏡」に映った、自分の内なる可能性を掘り起こし、そうして生まれる自己表現を、自分の好きな分野に利用することができるところに、パントマイムを演じる魅力はあります。
ぼくたちの「カンジヤマ」というのは、「“感じる”心が“山”もり」になったマイムという意味を込めて名付けられたもので、公演先の主催者には「感動が山もりでなければ、お代は要りません」とお伝えしているくらい、全身全霊を込めて活動しています。ステージを駆け回り、時には大声を出し、全身で感情を表わしているので、公演を終えた後は、もう汗びっしょり(笑)。観客の皆さんと一緒になってショーを形作っています。
また、落語協会にも正規会員として属していて、話芸も用いた演芸場用のマイムもおこなったり、早稲田大学や上智大学で、それぞれマイムの歴史と理論の講義を担当したりと、パントマイム三昧(ざんまい)の幸せな毎日を送っています。
――藤倉さんは人生のすべてを、パントマイムに捧げていらっしゃる。
藤倉健雄氏:パントマイムに魅せられて40年以上。今でこそ、自分が感動したこの道を歩むことができていますが、最初から将来のビジョンが描けていたわけでも、突出した才能に恵まれていたわけでもありません。そんなぼくが、今こうしてパントマイムで大勢の観客の前で表現し、感動を分かち合う機会を持てているのは本当に幸せなことだと感じています。 もちろん、ここに至るまでは、決して順風満帆ではなく、途中には投げ出したいほどの辛い出来事も確かにありました。それでもこの道を歩くことをやめなかったのは、パントマイムの中に見た「憧れ」が、強烈に自分の中に根を下ろしていたからなんです。はじめてパントマイムを目にした時の衝撃。「自分もパントマイムがやりたい!」。この単純で強い憧れこそが、ぼくのすべての出発点でした。