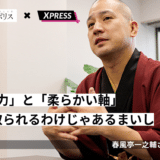「学問は身を助ける」
好きなことをやり切る素地を作ってくれた母の教え
藤倉健雄氏:パントマイムに出会うまで、ぼくは野球と英語に夢中になっていました。ちょうど『巨人の星』世代で、小学生の時に最初にはまったのが、野球でした。ただ、実際にプレイするよりも、「なぜカーブは軌道を描いて曲がるのか」といった理論の方に興味があって、同級生たちが『巨人の星』の登場人物になりきって練習している中、ぼくは理論書を読みあさって、頭の中でも野球をしていました。
次に興味を持ったのは英語でしたが、これは中学生の時、英語の教育学者である松本亨先生の『英語の新しい学び方』(講談社)という本を偶然手にとったことがきっかけでした。この時も、取り憑かれたように英語に関する本を片端から読みあさり、それでも飽き足らず英語塾にも通わせもらい、さらにはネイティブの先生から本場の英語を学びたいからと親にせがんで、学費は高額でしたが、私立で英語教育が盛んな立教大学の附属高校である、立教高校に進ませてもらいました。
――とことんやる性格は、パントマイム以前から……。
藤倉健雄氏:これには、ぼくの母の教育方針が大きく影響しているんです。ぼくの実家は、千葉県松戸市で江戸時代から七代続く「畳店」で、三人姉妹の長女だった母は、「職人に高等教育は必要ない」と、勉強したくしてもできない環境で育ったそうです。長男であるぼくも、将来は暗黙の了解で畳店を継ぐことになっていたのですが、母は「同じような想いをさせたくない」と、「学問はあなたの身を助けるもの」「そのためならお金に糸目はつけないから、好きなだけやりなさい」と、幼少時、近くを流れる坂川を散歩するたびに繰り返しぼくに言っていました。「勉強だけでなく、自分がこれと思ったものは、何でも納得するまでやりなさい」とも。今思い返すとそうした母の想いがあって今のぼくがあるんだなと、感謝しています。
英語にどっぷり浸かっていく中で、英語を駆使して世界で活躍できる同時通訳者に憧れ、英語の勉強にますますのめり込むようになりました。そのころには、ぼくの中で「畳店」を継ぐことはもうほとんど頭になかったのですが、いよいよ大学進学をすることになり、家からも半ば、仕方がないと思われるように。とはいえ、本当に好きだった英文科に進むことはなんとなく罪悪感があって言い出せず、「就職に有利だから」と繕って、あまり興味のない学部に進んでしまいました。 なんとなく、附属からそのまま進んだ大学。
ちょうど同じ時期に、同時通訳という職業が自分には向いていないことにも気づいてしまいました。同時通訳者は逐一話者の言うことをそのまま伝えることが仕事で、感情も私見も入り込める余地はないことに、ひと言付け加えてしまいそうな自分の性格では無理だと感じたんです。 せっかく許された大学進学。入学早々にして、ぼくは目標を見失ってしまったんです。興味のあった分野で選んだ学部ではなかったので、講義にも身が入らず、ほとんど出席していませんでした。その代わりに、単位にならないけれど本来興味のあった英文学関連の講義を受けたりしていました。
今につながる最初のきっかけとなったのも、もぐりこんで受けていた他学科の講義でした。英文科の鳴海四郎先生(当時文学座顧問)の講義で、アメリカの戯曲、マレー・シスガル作の『タイピスト』を鑑賞したのですが、人間の人生をわずかな時間に凝縮して魅せる、「創造的歪み=Creative distortion(※藤倉氏造語)」に魅せられた最初の出来事で、鳥肌が立つほど感激しました。こうした経験が少しずつパントマイムとの出会いにつながっていったんだと思います。
「感動の種」に水をまいてくれたパントマイム
情熱はすべてを動かす原動力になる
藤倉健雄氏:すっかり演劇の持つ魅力に取り憑かれていたぼくは、友人から「ちょっと面白い舞台を観に行かないか」と誘われて、その後のぼくの運命を大きく決定づける、ある演劇を観に行きました。それは、パントマイムの世界的巨匠マルセル・マルソーのパントマイム公演でした。 演目の一つに『青年、壮年、老人、死』というものがあり、「タイピスト」で見たよりも、さらに人生の機微を凝縮したパントマイム、彼の息づかい、そして息を飲む展開に衝撃を受け、見終わった後、ぼくはしばらく固まっていました。内容もさることながら、それに感動できる自分の内なる想い、「感動の種」を発見できたことがとても嬉しくて、それまでの無為な日々から救ってもらったような気分でした。そして心の底から感じたんです。「これがやりたい! こんな風に、人に驚きと感動を与えられる人間になりたい」と。
――ようやくパントマイムという「次に進むべき道」が見つかったんですね。
藤倉健雄氏:見つかったのはよかったんですが、パントマイムを本格的に学ぶための学校は当時日本にはなく、そのほとんどはアメリカかフランスにしかなかった。とことんやるためには大学を辞めて、留学しなければなりませんでした。ただ、それを親にどう切り出すか。そもそも、ぼくが家業を継がないことを薄々承知のうえで大学に進ませてくれたのに、今度はせっかく入った大学を辞めて、しかも家族の誰も知らない「パントマイム」を学ぶために、アメリカに行きたいなどと、どう考えても理解されないことを伝える勇気がなかったんです。
ただ、ぼくのそうした鬱積した想いは身体に影響を及ぼし、とうとう顔面神経麻痺として表れてしまいました。幸か不幸か、その症状のおかげで、結果的にはパントマイムへの想いを親に伝えることができたのですが、期待を裏切ってしまったようで、本当に申し訳なかったですね。それでも、「自分が心底感動させられた」世界を見てしまった以上、そのまま不本意なことをやり続けるわけにはいかなかったんです。 はじめて心の奥底を揺さぶられ、自分で見つけたパントマイムへの道は、自分の力で掴みたかったので、渡航費用と学費は自分で稼ごうと決めました。当時池袋にできたばかりの商業ビル「サンシャイン60」で、昼はエレベーターボーイ、夜は警備員と、寝る間も惜しんで働いていましたが、まったく苦ではなかったですね。「とにかく早くアメリカでパントマイムの真髄を学びたい」、その一心で働いていました。
情熱のすべてを捧げて誕生した「カンジヤマ・マイム」
藤倉健雄氏:朝昼晩働いて得たお金を貯金し、その合間に英語の勉強もして、ようやくアメリカに渡ることができたのが1年後。留学先は、稼いだ範囲内で通え、かつ最高峰の学びを得られるニューヨーク州立大学に決めていました。すべてをパントマイムに捧げるつもりで行ったので、大学での授業はもちろん、生活すべてに至るまで、アメリカでしかできないことを、とことん学んで帰ろうと思っていました。
マルセル・マルソーの愛弟子であるアメリカパントマイムの巨匠、トニー・モンタナロ氏に師事することも、大学の教授に勧められました。これもアメリカでしかできないことのひとつでした。大学を卒業後は、さらに学びを深めるために同大学の演劇学部の修士課程に進み、その2年間では大学の学部でマイムのクラスを教える機会にも恵まれました。この時に、マイムを演じるだけでなく、教えるという今のぼくの軸ができあがったんです。 大学院も無事修了して日本に帰国する段になり、師匠であるトニー・モンタナロから、「感じる心が山もりのパントマイムを日本で広められるように」と、名付けられた「カンジヤマ・マイム」はこの時に生まれました。1985年、ぼくは27歳になっていました。