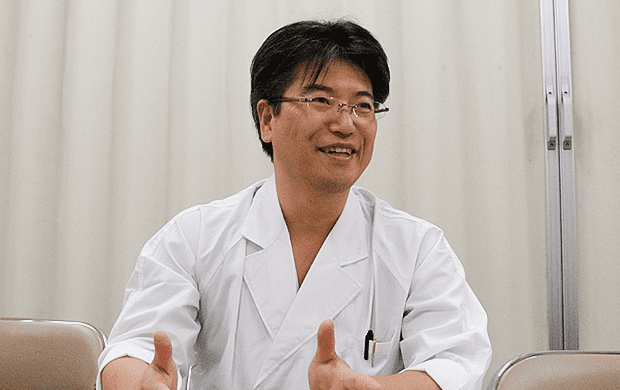新しい“発見”と“最適解”を求めて
――友達についていって始まった大学生活(笑)、いかがでしたか。
数岡氏:何もかもが新鮮でしたね。高校時代に生物を選択していなかったので大変でしたが、授業は楽しく感じました。またこの頃は、はじめての独り暮らしということもあり、ご多分に漏れず“学外の”学生生活も謳歌していたんです。授業よりもハマったのが、下宿先に近く、賄い付きが魅力ということで、はじめた飲食店でのアルバイトだったんです。
これがいざやってみると、どんどん面白くなって……。一時、バイト先のシェフから「数岡君は包丁さばきが特に上手いから、大学を辞めてこの世界を目指してみないか」とおだてられもしました(笑)。物理の世界もそうなのですが、「こんな世界、こんな考え方があるんだ」という“発見”が面白くて、この時もそんな感じで「料理」にのめり込んでいったんだと思います。
ただ、のめり込んだツケは大学の中盤に成績となってしっかりと表れました(笑)。それで、奨学金も借りていたし「これではまずいだろう」と、学生の本分に戻るため、時間を割いてしまう飲食のアルバイトからは手を引いたんです。とはいえ、奨学金だけでは学生生活を続けていくには不十分で、やはりアルバイトも必要でした。そうした状況の中で考えたのが、「短時間で稼げる、単価の高い家庭教師になること」だったんです。
――今いる状況の中で、最適解を見つけ出す。
数岡氏:バイト代の単価を上げるための工夫というか、ただ必要と思われることをしたんです。やはり、家庭教師の実績は「合格者の数」に尽きますので、できる限り合格する可能性が高まる、教え子が実現可能そうなプランを自分で考え出したりしていましたね。おかげさまで、普通の家庭教師の相場をかなり上回るのお給料をいただくことができ、自分の勉強にも集中できるようになりました。
この時に、研究の世界に興味を持つきっかけになったのが、酵素の分野の世界的権威である左右田健次(そうだ・けんじ)先生の授業と、左右田先生の指導を仰ぎながら行った卒業研究でした。先生は、元々京都大学にいらっしゃった方で、退官後、名誉教授として、私が進んだ新設の生物工学科に来られていた方でした。左右田先生の学生を惹き付ける授業を受け、酵素の世界に興味を持ったことが、研究者としての扉を開く大きなきっかけとなったんです。
偶然を楽しく。「制約」の中で広げた道。
数岡氏:左右田先生に出会えたことは幸運なことでしたが、自分がこの世界を目指すうえで、大きく影響を及ぼしたのが、家族の存在でした。どの家庭にも、進路や将来の選択において、金銭面やその他さまざまな事情があると思いますが、自分の場合も、家庭の事情で、ある種の「選択の制約」があったんです。
家族と一緒に住むことだけではなく、家族の生活のために多くの時間を確保できること、かつたくさん必要な医療費のために安定的な収入も得なければならないという制約の中で、自分の好きと両立できる道だと考えたのが「大学の教員」でした。そこから、大学の教員というゴールにたどり着くまでの道のりを「妄想」で設定し、それを進んでいく日々が始まりました。
関西大学からそのまま大学院まで進み、ドクター(博士号)を修了した後、幸運にもポスドク(※ポストドクター。博士号を取得しながら、非正規の立場で研究活動を続ける任期付き研究者)として、京都大学の江﨑信芳(えさき・のぶよし)先生の元で研究員を1年間、その後、2年間という任期付でしたが、京都大学の科学研究所で、講師として教務職員のポストに就いていました。
ポスドク問題もあって、周りは多くの優秀な研究者たちだらけの中で、正直先の見えない細い道を進んでいるようで、この頃は不安な毎日でしたね。
――不安を抱えながら、「細い道」を信じて、進んでいく。
数岡氏:とことんやってダメなら諦めて、別の道へ進む。けれど、可能性があるのならやりきる。私は、特別才能に恵まれていませんが、ただ、やるべきことをやり続けてきました。研究者のやるべきこととは結果を出すこと、実績を重ねることなので、とにかく「才能がなければ誰よりも勉強」と、すべてを研究と勉強に費やしていましたね。
自分が持っている能力や、状況の範囲内でやることをやっていけば、急激な変化を望めるほどの能力はなくとも、時間をかけて緩い坂道にすることで、その道を作っていくことで羽ばたくことができる。そう思って、なんとか細い道を探りながら進んでいました。
結果的に、その細い道は、三つの大きな道、人生の選択肢となりました。京大でポスドクとして残り酵素の研究を続けること、内定をいただいていた世界規模の酵素を研究・開発する企業に就職すること、そしてもう一つが、ここ農大での研究・教育職だったんです。
正直、研究という側面ではどれも魅力的でしたが、私の家族に関係する制約の中で一番の最適解となるのが、農大で働くことだったんです。そうして、2006年、いくつもの偶然が重なって、私はここ東京農業大学の酒類学研究室で、日本酒の世界と関わることになっていったんです。