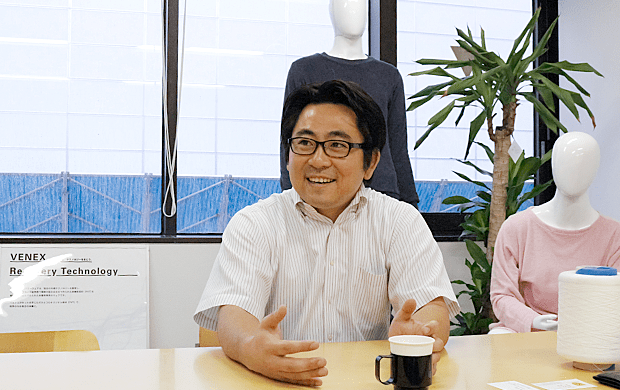「行動のみが世界を変えていく」――。世界初の特許素材を用いた「リカバリーウェア」を開発した、ベネクス代表の中村太一さん。発売以来、多くの著名なアスリートの間で人気に火がつき、世界でも爆発的なヒットを記録した革命的スポーツウェアには、どんな挑戦があったのか。借金1億円超えから、累計45万着の大ヒットに至るまで。予想外の連続を乗越えた行動力の源とは。(アルファポリスビジネス配信記事です。写真/Hara・アルファポリス)
こんな話をしています……
・出会いは独創的な発想でもひらめきでもなく、すべては「行動」が引き合わせてくれた結果だった
・せっかく助かった命をとことん生き抜こう。「いつ死んでも大往生」だと思える人生にしていこう
・すべてが均一化されて便利になっていく世の中に、新たな穴を掘ることで、それまでにない価値や習慣を提案する
中村太一(なかむら・たいち)氏プロフィール
株式会社ベネクス代表
1980年、神奈川県小田原市生まれ。慶応義塾大学商学部卒業後、コンサルティング会社に入社。同社の運営する有料老人ホームの立ち上げ、営業を経て、家業の繊維問屋を継ぐ。2005年、株式会社ベネクスを設立。開発した新素材PHT繊維は、世界34カ国で特許を取得し、「リカバリーウェア」として、世界で“革命的なスポーツギア”と評され、ドイツのISPOで日本初の最高賞「ゴールドウィナー」を受賞。日本パラリンピックオフィシャルサポーター。ドイツ水泳協会のオフィシャルパートナーを務めるなど、次の時代を担う創造企業の代表として、自ら行動・挑戦し続けている。【ベネクスコーポレートサイト】。
世界が驚いた“リカバリーウェア”は予想外の連続だった
――「リカバリーウェア(回復する服)」が話題です。
中村太一氏(以下、中村氏):私たちが製造、販売するリカバリーウェアは、PHT(プラチナ ハーモナイズド テクノロジー)という、世界34カ国で特許を取得した新特殊素材でつくられています。ナノプラチナなど、粒子状の鉱物を一定の割合で繊維に練り込んだもので、鉱物の発する電磁波が自律神経の「副交感神経」のはたらきを高め、血行促進や免疫細胞の活性化に作用することに着目して開発されたものです。
2009年に、運動後の休養時専用ウェアとして発売以降、日本代表選手をはじめとするスポーツ関係者に愛用され、今ではアスリートだけでなく、日々の疲労軽減や安眠効果から、高齢者や主婦、ビジネスパーソンにも広がり、おかげさまで全世界で45万着を突破しました。
――特許技術と独創的なアイディアが用いられています。
中村氏:もともと私がいた介護業界での経験から「寝たきりの高齢者の床ずれを解消したい」という想いが生まれ、それを解消する介護用ベッドマットの開発に着手したところから始まりました。ところが前例のないアイディアに対し、大手の素材会社や開発会社からは門前払いの日々。なんとか開発まで漕ぎ着けるも、その後「ある誤算」から、渾身の作だった会社の主力商品がまったく売れず、と予想外の連続でした。
開発から日の目を見るまでの間、協力してくださった大学の研究者や企業の方々、行政やバイヤーさんなど、多くの方々に支えられました。こうした出会いは独創的な発想でもひらめきでもなく、すべては「行動」が引き合わせてくれた結果だったように思います。そしてそれは、自分自身が「ある日突然人生が終わるかもしれない」と感じた経験が、原点になっています。
「将来は自分の思い描いた通りにしかならない」
中村氏:うちは代々、親、親戚含め起業一家でした。起業といっても、何か新しいアイディアで勝負するというよりは、世の中の需要を商売に結びつけていくという感じでした。食卓の話題にのぼるのはいつも、商売の話。そうした空気の中で私は育ちましたが、親の仕事を継げと強制されたことも、起業のための特別な教育を受けた記憶もありません。ただ、唯一何度も口癖のように言われていたのは「将来は自分の思い描いた通りにしかならない」という言葉でした。
――その言葉は中村さんの起業の源にもなっている。
中村氏:その時はそれほど意識していませんでしたが、「自分がやりたいと思うことに対してリミットをかけない」ということ、そして「将来は自分が思い描いた通りになるんだ!」という妙な自信は、知らず知らずのうちに育てられていたのかもしれません。
「やりたいことは何でもやる」。幼い頃は、考えるより手足が先に出るような性格で、外を遊び回っていて生傷の絶えない子どもでしたね。そんな有り余るエネルギーを、学生時代にぶつけていたのがラグビーでした。他のスポーツのルールは物足りないものでしたが、タックルしてもぶつかっても、それがプレーとして評価されるスポーツに出会えたことが、その後に繋がる一つの大きな節目になりました。
九死に一生を得て芽生えた意識
――自分のエネルギーをぶつけられるものが見つかった、と。
中村氏:その当時はひたすらラグビーに明け暮れていましたね。高校生になるとさらに花園を目指して生活はすべてラグビー一色。ところが、高校2年生の時に出場したラグビーの県大会決勝戦で、「ピリオド」は突然訪れました。
決勝戦ということもあり、いつも以上に張り切ってしまったのかもしれません。試合中、激しいタックルで相手選手と衝突したのですが、打ち所が悪く意識を失ってしまい、そのまま救急車で病院に運ばれたんです。
精密検査の結果は問題なし。ところが検査の翌日、いつもと同じように電車に乗って駅に向かったところで「異常」に気がつきました。改札で定期券が手から滑り落ちたのですが、その後何度拾おうとしても指が思うように動かなかったんです。
手と脳が繋がっていないような感覚。ショックでした。実はその時、脳の硬膜が破れ出血を起こしている状態で、命の危険に晒されていたんです。しばらく経過観察が必要でした。そんな中、奇跡的に大きな手術にもならず、一命を取り留めることができましたが、この事故以来、激しいスポーツは一切禁止。もちろん大好きなラグビーの道も、この日を境に絶たれてしまいました。
――突然、自分の居場所がなくなってしまった……。
中村氏: ラグビーの夢も断たれ、しばらくはエネルギーを向ける矛先を失い、やる気が起きず、正直腐っていました。そんな状況を変えたのが、短期留学で向かった、イギリスでの生活でした。どこか別の場所、文化も言葉も違う景色のなかで過ごしたいと思っていました。そこで、いろいろな人と触れ合う中で、少しずつ事故に対する向き合い方が変わっていったんです。
自分は死んでもおかしくなかった状況で、今こうして生きている。せっかく助かった命をとことん生き抜こう。「いつ死んでも大往生」だと思える人生にしていこうと、この時強く思ったんです。そうして「自分の生きた証」を残したい、何か「社会に楔(くさび)を打ちたい」という想いを強く抱くようになりました。
大学時代は、その「何か」を求めて、思いつくことは何でも行動に移していました。家族旅行で行った海外で面白そうなものを大量に仕入れて、フリーマーケットで売りさばいたり、何事も経験だとさまざまなアルバイトをしてみたり。あの事故をきっかけに「失敗したからといって命までは取られまい」という想いが、自分を動かしていましたね。